どうも、ぞーげきゅうです!
私はパキポディウム・グラキリスが大好きで、いつか “自分の大切な株から種を採って実生し、現地球のようにカッコよくて立派な迫力ある姿に育て上げる!” ことを夢見ています。
そうやって良質な実生株を安定して育てることができるようになれば、グラキリスの国内実生株の普及にも何らかの形で貢献したいし、それが回りまわって自生地の生物としての種の保存に少しでも繋がればいいな、と思っています。
…と、そんなぼんやりとスケールの大きな目標を描いていますが、この度、ひとまずこれに向けたはじめの一歩となる「自分の株から種を採る」ことに成功しました!
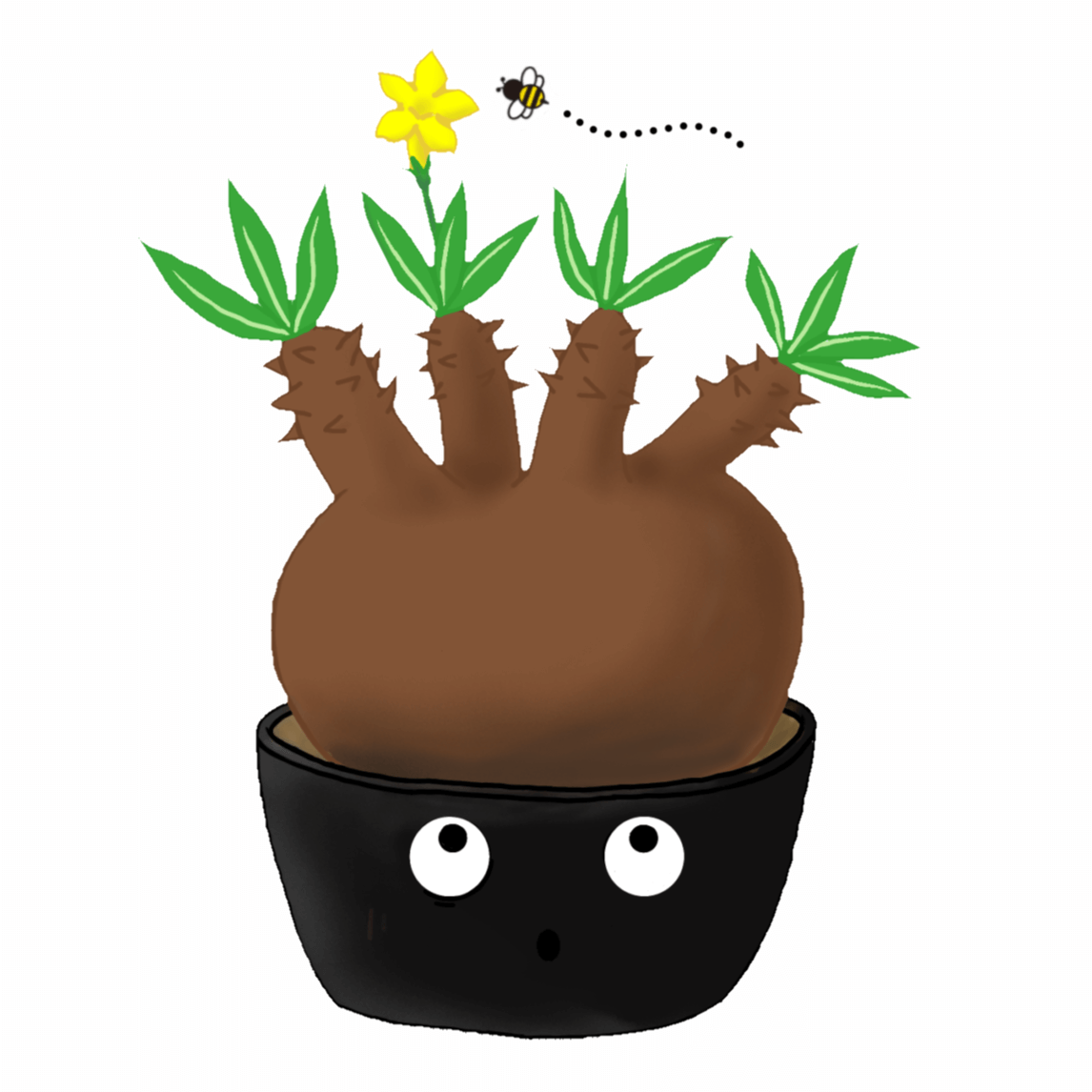
いやーしかし…、こうやって日頃手をかけて育ててきた株から種が採れると、やっぱり嬉しいものですね!
人工授粉での結実
今年の春は意図せず例年以上に花つきが良く、絶好の授粉チャンス到来でした。また来年以降もたくさん咲いてほしいものです。
そして以前こちらの記事で、初めての人工授粉に挑戦したことを書きました。
今回はこの続報ということになりますが、この時点では、次の2ペアで授粉作業をしていました。

左の実生株はまだ小さいため授粉させず、花粉だけ採って右の親株へ授粉。

どちらも塊根の丸い良形。
1枚目のペアが自身初めて経験する授粉作業でしたが、予想以上に難しくて全く手応えがなく、後に結果としてやはり失敗していました。
2枚目のペアでの授粉では少しコツを掴み、こちらは片方(写真右の株)で結実。
これに加えて後日、さらにこの3株で授粉作業を行いました。

左2つは2枚目の写真と同じ株で、右の株が新しく加わった。

それぞれの総当たりで掛け合わせ、各2花ずつ授粉作業実施。
3回目の授粉作業ということで、ある程度慣れてきて授粉のやり方も確立できていたため、この日の分は結果的に全て結実しました。
※ただし最終的に種が採れたのは、3株のうち1枚目左(2枚目下)の株のみでした。
授粉・結実以降の経過
授粉がうまくいった場合、花弁が落ちたあとに種鞘が膨らんで伸びてきて、最終的に鞘が弾けて種が採れることは知っていました。しかし、その過程がどれくらいのペースで進んでいくものなのかが分かりませんでした。
ということで、今後の目安のためにも、今回の経過を簡単に記録しておこうと思います。
順調に育った種鞘
上の写真左の株では、3つの花で授粉を行い、全て成功。
時系列で振り返ると、その後はこんな感じで種鞘が伸びていきました。
子房が膨らんで結実を確認できたのが、授粉作業から2週間経過した頃でした。

その1週間後。
花弁が取れた両サイドの子房は、この時点で膨らんでいるのが分かりやすいですね。

さらに1週間後。
気温も上がってきたからか、ぐんぐん鞘が伸びています。

ちなみに、ひとつの花柄・子房から種鞘は2本伸びてくるので、3つの花で授粉した今回は種鞘が計6本。
さらに1週間後。
授粉から1ヶ月以上で、手のひらに対してこれくらい。
そろそろ弾けてもおかしくないサイズかな?と思い、排水溝用の水切りネットを取り付けました。

そしてここからが長く、さらに3週間後。
授粉からちょうど2ヶ月で種鞘が割れて弾け、中の種が出てきました。

1ヶ月を過ぎたくらいからは種鞘のサイズもほとんど変わらず、待てど待てど鞘が弾けないので、いつになれば種が出てくるのだろう…?と少し心配になりました。
しかし、最後は数日のうちに鞘が急に黄色く枯れ込んで、割れました。


ということで、この株の種鞘は無事に育ってくれました!
そして、親株として今回授粉させた残りの2株は、最終的には種を採ることはできませんでした。
【虫の影響?】突然、落ちた花茎
まずは、こちら。

これは、もう一つの良形グラキリスから伸びていた花茎です。
授粉から10日ほど経過したある日、この株の鉢を移動させて棚に置いた瞬間!、「ポロッ…」と花茎が私の腕の上に落ちました。
「…ん?…、えーっ!?」と一瞬何か起こったか理解できませんでした(笑)

授粉をさせた2つの花の両方で子房が膨らみ始め、結実が確認できていたので「よし、この株も授粉がうまくいってる!種が採れそう!」とワクワクしていた矢先の悲劇でした…(笑)


これに関して、原因が気になって調べていると、ハダニが付くと花茎が落ちやすくなるという情報に行き着きました。
そして、この株ではまさに春先にハダニが発生していました。
順調そうな花茎があまりに突然落ちたので、他の株の花茎もいつダメになってもおかしくないと思うと、常に不安でした…(笑)
【双子花の影響?】結実するも枯れた子房
次に、種が採れなかったもう一つの株。
こちらも授粉させた2つの花はどちらも結実したようで、子房が膨らんでいました。
しかし、だんだんと色が黄色くなっていき、そのまま枯れてしまいました。

この株では虫は見られませんでしたが、上の写真のとおり、1本の花柄が枝分かれして2つの花がついていました。
授粉は成功したものの、この影響で種鞘を形成するための栄養が不足し、枯れていったのかも知れません。
授粉作業を行うときにも、「双子みたいに咲いてるなー」とは思っていたのですが、他の株と開花のタイミングが合ったので、授粉させてみました。
次回以降は、こういった花では授粉させないようにしようと思います。
ついに種が採れた!(計100粒以上)
ということで、ついに自分の株から種が採れました!
鞘から弾け出てきたばかりの種には、ふわっふわの綿毛がついています。
これが風に乗って本当に簡単に飛んでいくので、収穫前のネットはやはり必須ですね。(笑)

第一弾(5月13日授粉分)
こちらは、5月13日に授粉させた花の種鞘が先に弾けて、採れた種。
綿毛を外して数えてみると、21粒ありました。
2本の種鞘でこの数なので、1鞘あたり10.5粒。

第二弾(5月22日授粉分)
その約10日後、残っていた5月22日授粉分の種鞘が弾け、この花茎から全ての種を採り終えました。

これも綿毛を外して数えてみると82粒あり、第一弾の鞘よりもたくさん採れました。
4本の種鞘でこの数なので、1鞘あたり20.5粒。

第一・第二弾を合わせると、今回採れた種は合計103粒!
結果的に採種できたのは1つの株だけでしたが、思った以上にたくさん採れました。
ちなみに第一弾の1鞘あたりの数が少なかったのは、鞘の先端に枯れた花弁帽子が最後まで残っていた影響もあるのかな?と考えたりもしますが、どうでしょうね。
過去の写真を見たり思い返してみても、特に鞘が小さかったり細かったという事はなかったとは思いますが、もしかすると拘束されて鞘が膨らみにくく、中で種子が実りにくかったのかも知れませんね。
初めて自家採種してみて
ということで、個人的に今年の目標の1つとしていた “所有株での人工授粉~自家採種” が叶いました!
今回特に印象に残ったのは、次の2点。
- 授粉作業がとにかく地味で繊細で難しい
- 結実しても種が採れるまで油断できない
授粉はそれなりにコツを掴めましたが、初めてだとかなり分かりづらいなと思いました。
種が採れるまでの一連の流れを経験できたので、今年うまくいかなかったところを来年以降はいろいろと改善していきたいと思います!
それと、今回授粉させてから種が採れるまでちょうど2ヶ月かかりましたが、結構かかるんだなという印象です。
授粉から2ヶ月かかるとなると、4月中には授粉作業をしておかないと、播種の適期である6月に蒔くことができません。なので、毎年安定して適期に採り蒔きしようと思うと、花芽形成~開花のタイミングもある程度コントロールが必要になるのかな?と、さらなる高みを眺めてみたりしています。(笑)
この授粉~採種までの期間については、今回は一つの花茎で3つ授粉・結実させたので、もしかするとその分、種鞘の成長が遅かったのかも知れませんし、また来年以降に色々試してみるのも楽しみです。
そう、それともう1つ、今回の重大なミスが…(笑)
種の♂親株がわかるように、授粉させた株の組み合わせを書いた札を花柄にかけていたのですが、先述のとおり突然花茎ごと落ちたときに「風で花茎があおられ続けて疲労的に折れてしまったのかも…」と考え、少しでも風を受けにくくするため、札を全部外したんですよね。
その後、種が弾ける頃にもう一度札をかけるか、水切りネットを種鞘ごとに分けてかけようと思っていました。が…見事に全ての種が弾けるまで、それを忘れてしまってました。(笑)

なので、先に弾けた21粒の種は親株が確実に分かるのですが、あとの82粒の種については♂親株がわかりません。(笑)とはいえ二択ですが。
…というこんなミスも、次回からは無いように気を付けたいですね。(笑)
以上、私の初めての自家採種についての記録でした。
実は、なにか自分の好きな生き物や植物を殖やしてみることが、私の幼い頃からのひそかな夢でした。それが今回叶ったということで、種が採れたときはとても感動しました。
これから、さらにこの種を自分の手で立派なグラキリスに育て上げてやりたいなと思います。
早速、次の挑戦の始まりです。植物っておもしろい!
ではまた!
-768x577.png)
-160x160.png)



コメント